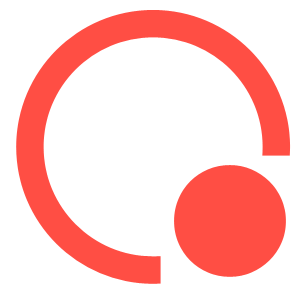簡単に説明するなら、この2分ほどの予告編を見れば必ず見たくなる。この美しいモノクロ映像と豚を中心とする生きのものの生態が、ナレーションもセリフも音楽もなく延々と映し出される。しかし
フレデリック・ワイズマン監督の『ボストン市庁舎』も全く演出のないありのままを映す映画だったわけだが、人為的な社会とこの自然の摂理を描く映画とでは全く違う。

このあたりのことは、映画が終わった後に評論家の森直人さんと
放送作家の
町山広美さんの解説で丁寧に説明されるのだが、冷静によくよく考えてみると、豚は人が食用に作った生きものなのだ。もともと豚はイノシシだった。それを人に安く提供できるように改良されたものなのだ。映画ではニワトリとウシについても描かれるのだが、いずれも人のために作られた動物なのである。そう思うととてつもなく恐ろしくなってくる。

そういう裏側を知らずに粛々とこの映画を鑑賞したら、きっと美しい映画というだけで終わるだろう。とにかく美しいのだ。聞くところによると、この映画は相当に演出が施されているようで、例えば光の加減などについては、その美しい映像はミラーボールなどを使ってかなり作り込まれた映像の積み重ねなのだそうだ。


このお二人の解説を聞いてまるで映画の見方が変わるのだが、たしかにこの映画に出てくる動物にはどこか欠落しているものがある。その象徴として片足しかないニワトリをカメラが延々と追うシーンがある。片足がなくても何事もなかったかのように生きるニワトリを追う。その傍らで、全く感じ方の違うシーンがある。

冒頭のシーンで豚小屋の窓から小さな豚が次々に現れる。母親が子豚をたくさん産み落とすシーンの最後に、わらの下に埋もれた子豚の声が聞こえて、母親はその子豚を探すため鼻でわらをよける。しかし埋もれた豚はまともに歩くことができないと知ると、母豚はなんと・・・・

この映画には全く人間の気配がない。しかし最後の最後に画面いっぱいにト
ラクターの巨大なタイヤが現れる。それは自然を破壊する都市化をイメージするような巨大な力だ。そしてタイヤの向こうで何が起きているかは映さず、子豚たちの小さな声が幾重にも重なってゆく。その声は映画のはじまりで聞いたはずの生まれたての可愛らしい子豚の声とはまるで違う声に聞こえる。そしてト
ラクターは大きな音をたてて去ってゆく。

子豚が連れ去られた後、残された母豚は周囲を声をたててさまよう。その声は鳴き声ではなく”泣き”声だ。低い位置からのカメラはこの母豚をワンカットで延々と追い続ける。泣き声をあげてさまよう母豚が最後にどうしたかは、映画を見ていただくしかない。これで映画は終わる。

映画を見終えて街の喧騒を歩くと、それがまるで違うものに見えてくる。この人達は、もちろん自分も含めてブタやニワトリやウシの肉を食べて生きている。生かされている。しかしそれは命のはずだ。動物に限らず魚だって植物だって命だ。生きているのだ。生きている生きものを残酷にも殺めて自らの口に放り込む自分たち人間の様を自覚させる。こうした動植物を口にして「おいしい」と・・・
最も地球上で罪深い生きものの思惑で人工的に生かされて殺されてゆく動物を、とてつもなく美しい映像だけで突きつけるこの映画のつくり手の意思を想像する。この映画は人の首元に突きつけられたナイフのような切れ味がある映画だ。
★
貼りました。みつけてみてくださいね。