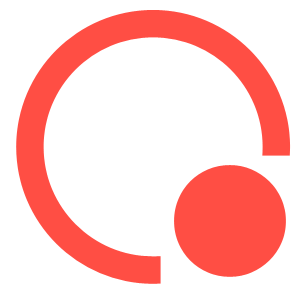『カモン カモン』 マイク・ミルズ
試写会で『カモン カモン』を鑑賞。監督はマイク・ミルズ。『20センチュリー・ウーマン』の監督。あの映画も親子の映画。母と息子、というテーマはこの映画にも重なる。
何も考えずに見るともっさりした映画だが、なかなか巧妙に描かれた人間ドラマだ。要するに親や大人は子供のことがわからない、というテーマ。
姉の息子ジェシを預かることになったジャーナリストのジョニー。ジョニーとジェシの話。この二人の噛み合わない関係こそ、世界の分断を意識させる。お互いは何もわからない。
ではその答えはどこにあるかというと「聞くこと」だ。ホアキン・フェニックス演じる主人公は子どもたちにインタビューするのが仕事だ。子供にマイクを向けてヘッドホンでその声を拾う。このインタビューシーンだけで映画にならないだろうか。すごく良かった。世界でパンデミックやジェノサイドが起きる絶望的な社会で、少なくともアメリカの子どもたちは色々なことを考えつつ、自分たちの未来の可能性を信じている。ここは胸が熱くなるシーンが断続的に表現される。活き活きした子どもたちの顔。そして大人顔負けの落ち着いた応答など、いずれも素晴らしい。そしてインタビューの対象が多様性に富んでいるものいい。ロサンゼルスとニューヨークの子供では答えが少し違うあたりも面白い。
ところが、ジョニーが預かるジェシは、どこか表情が冴えない。そして大人が思うようには動かない。大人側から見るジェシの言動はまるで理解ができない。ジェシは自分の母親と精神的に病んでいる父親にストレスを感じている。ジョニーも自分の母親との思いでに齟齬がある。認知の母親を介抱するシーン、母親の目線がカメラをじっと捉える。あの目こそ実は子供が大人を見る目なのではないか。ジェシがときどき見せる表情と認知の祖母(ジョニーからすると母親)の存在がとても気になる。老いて全てを忘れてしまう母と、多感なジェシの間には子供が大人になり、そして老いてゆく人類の、あるいは生き物そのものを抽象化しているように思わせる。
この映画はあまりにも情報が多すぎて消化できない面もあるものの、とらえようとするドラマは極めて普遍的だ。『20センチュリー・ウーマン』も母親が子供を理解できないので、いろいろな人を介して理解しようとるす。この映画『カモン カモン』のジョニーもまた同じだ。子供の頃に気づかなかったことは大人になると忘れてしまう。忘れたことを子供を介して呼び起こそうとする映画だ。
自分に置き換えても、もう子供だった頃の記憶は薄れている。あの頃大人だった伯父や伯母。両親もそうだが、もう子供から見る大人ではなく、大人として当時の大人を見ている自分に気づく。極めて矛盾した話だが、人とはそういうものだ。そしてさらにこの映画は、世界の分断がコミュニケーションを失っていることもまた暗示する。
そう考えると、とてつもなく深い映画だ。『クレイマー・クレイマー』が懐かしく思える。
(=^・^=)
★
貼りました。みつけてみてくださいね。
The Windshield Wiper アルベルト・ミエルゴ
今年のアカデミー短編アニメ賞に輝いた、スペイン系アメリカ人のアルベルト・ミエルゴ監督作品The Windshield WiperをYouTubeで見ることができた。15分の短編。
”愛する”という甘い言葉とは裏腹に、愛という形の現代の在り方をたった15分で奥深くまで掘り下げようとするドラマ。はっきり言って恐怖映画だ。

ミエルゴ監督はインタビューで丁寧にそのことを説明されている。
Hollywood films are full of accidental encounters, but nowadays because of technology and changing societal codes, it’s maybe made it more difficult to meet people. Yet dating apps are also connecting you with people you might never see in your life, so I have a very mixed feeling about this.
ハリウッド映画は偶然の出会いでいっぱいですが、今日ではテクノロジーと社会規範の変化により、人々との出会いがより困難になっている可能性があります。それでも、出会い系アプリは、あなたの人生では決して目にすることのない人々とあなたを結びつけているので、私はこれについて非常に複雑な気持ちを持っています。
CARTOON BREW

これは何を言っているかというと、スマホで出会い系サイトを見ながら買い物をする別々の男女がいて、この二人は見事にマッチングする。しかし、目の前にマッチングした対象がいるのに気づきもせずに別々の方向に去ってゆく。これを恐怖といわずなんというのか?

表現の不自由展④ マネキンフラッシュモブ
そろそろ最後にしよう。「もう終わりにしよう」
フラッシュモブの話題で終わる。
彼らのパフォーマンスは笑わない(バスター・キートンのようだ)、動かない、しゃべらない。海老名駅の自由通路で行われたパフォーマンスを行政が違法だと主張するので、彼らは裁判で勝訴し、行政側を突き倒した。彼ら行政も見えないものは違反だと思い込む。見たことも聞いたこともないものやことに対応できない。
「平和の少女像」 やTPP問題などについても同じ活動をしていて興味をそそる。


こうした彼らの活動もまた、権利を守ることに通じている。
そしてありとあらゆる表現があって、対立意見であっても認め合うという文化や国民性を築き上げないと、いつまでもあるべき論の原理主義的な対立でお互いが傷ついていくだけだ。

なんども言うが、自分はこの国が好きだ。そしてこの国を守りたいと思う。しかしそのために対立軸を作って黒いものを白く塗り替えたり、存在を透明にして消し去ったりすることは本位ではない。この少女像でさえ、最初見たときは気持ちがぐらついたが、下品などこかの市長のおかげで、まるで違う存在に思えてきた。特に日本人は見たこともないものを嫌悪する。


どんなものでも初めて見るものは異質だ。しかしそれをじっくり見つめればそれぞれに意味がある。今回の展示で過激な暴力行為があるとしたら、それは「無知」がもたらす悲しい行為である。これらの展示を嫌うことを否定はしないしその考えは尊重する。しかし過激な思想やテロ行為などの暴力で、何もなかったように消し去ろうとする傲慢な姿勢だけはいかがなものかと思う。とても残念に思う。


昭和天皇をデフォルメしたこれらの作品だって、個人的には必ずしも気持ちがいいとは思えない。しかしその存在を認めることで、自分とつくり手の変化を感じるものだと思う。どんな考えや思想や表現も消し去ることはできないのだ。
(=^・^=)
★
貼りました。みつけてみてくださいね。
表現の不自由展③ 小泉明郎
まだ続く、「表現の不自由展」。実は相当頭に血が上っている状態である。
ここで自分の意見を展開するつもりはないが、自分はこの国を猛烈に愛している。正月の一般参賀にも行くし、皇室の話題があればそれに目を向けて微笑んでいる。だからといって天皇制を批判する意見に聞く耳を持たないというわけでもない。それは個々の考えであり思想だ。愛国者であってもアンチな意見に興味はある。少なくとも自由表現まで弾圧されることがあってはならない。憲法にも保障されている行為。かつて大島渚が『愛のコリーダ』で戦ったことも同じ文脈にある。あの映画にも戦争の影が見える。
その意味で前山忠の反戦シリーズが過激な作品ではあると思う。



皇室ご一家の写真から人物を切り抜くとは、さすがに衝撃的だが、このカンパ入れの箱が展示側も規約に違反するとかのいわれなき理由で撤去されてしまった。いま最も世界の人々が唱えなければならない反戦の願いが閉ざされる。逆さから見れば、撤去した側は戦争に猛進したいという意思なのか?

小泉明郎のこの作品は衝撃だった。「空気#18」は合成写真である。福島に慰問に来られた天皇皇后両陛下に頭を下げる先には両陛下がいるはずだが、透明化してしまった。これには深い意味がある。放射能という透明で見えない空気と、両陛下の透明度をかけ合わせている。日本人にとって天皇制は透明な空気のようなものだが、放射能もまた透明な空気だ。

白川昌生の「群馬県朝鮮人連行追悼碑」は歴史修正主義を意味している。もともとあった追悼碑をクリスト風にかばうことで主張するのだが、その展示が取り消されるという事件が発生する。表現の自由の撤回を裁判所に訴え、一審判決は違法とされるものの、高裁では請求が棄却されている。
いま裁判所を舞台とする憲法21条問題はせめぎあいをしているらしい。この展示が大阪で展開されたときも、名古屋のバカ市長と同じで、大阪の府知事も歴史修正主義的な立場を明らかにして、表現を圧殺する意思を示している。ここは極めて危険なところだと思う。これで法解釈までが捻じ曲げられると、さらに日本は終わりに向かうだろう。
そういえばこの展示会には複数の弁護士が待機していた
★
貼りました。みつけてみてくださいね。
表現の不自由② 大橋藍ほか
表現が閉ざされた作品は「平和の少女像」だけではない。たまたまあいちトリエンナーレで注目度が上がっただけだ。逆説的にいうと、この状態を世間に知らしめる役割をあのあほんだらの市長は担ってくれたのかもしれない。◯◯となんとかは使いようだ。
この小さな展示ホールの中でお腹いっぱいになるほどの情報が掲げられているのだが、過去の検問年表(検問という言葉事態も前時代的だが・・・)を見ると、戦後1950年から始まっている。

そしてその矛先は、学生の卒業制作にまで及んでいるらしい。大橋藍さんの「アルバイト先の香港式中華料理屋の社長から「オレ、中国のもの食わないから。」と言われて頂いた、厨房で働く香港出身のKさんからのお土産のお菓子」はあいた口がふさがらなくなるような作品だ。

大橋藍さんがひとりひとり丁寧に説明されている姿が健気でもらい泣きしそうになる。(写真の左下の足元は大橋藍さん)この作品のタイトルをもう一度整理するが、社長とは日本人だ。日本人の中華料理店の社長が「中国のものを食べない。」と香港土産に嫌悪感を示す。この社長の頭のレベルはともかく、これは無知からくる偏見そのものだ。この社長は恐らく台湾と中国の違いもわからず中華料理店を営んでいるのではないだろうか。それにしても「中国のものを食べない。」とはどういうことだろう。

丸木位里+赤松俊子作「ピカドン」は1950年の作品。共産党機関紙「アカハタ」の影響で処分を受けた作品。
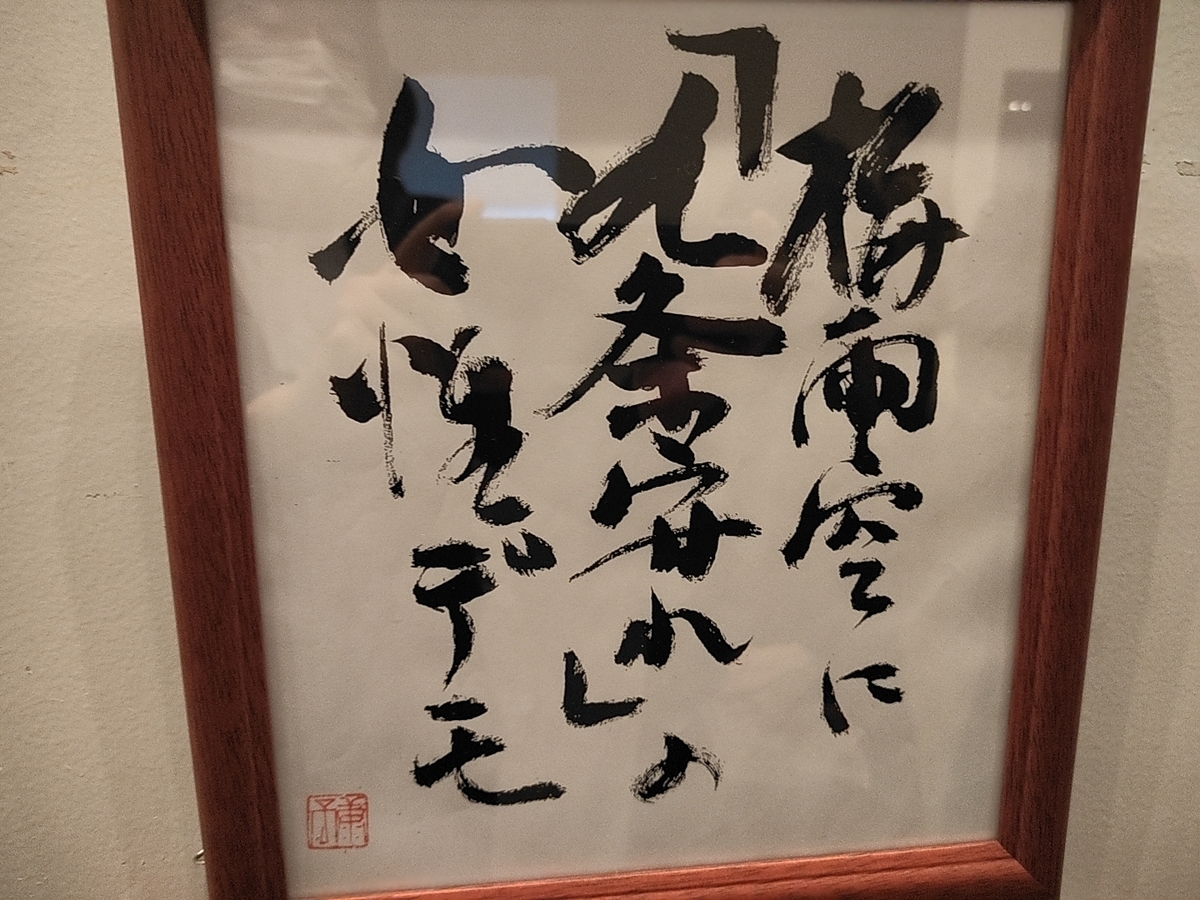
「九条俳句」はしびれる。詠み人知らずだが、俳句サークルで1位に選ばれながら、公民館から展示を拒絶される。



豊田直巳の「叫びと囁き」はまさにベルイマンの映画タイトルのようだ。豊田氏はチェルノブイリの原発事故なども記録している方で、この福島を題材にした作品の中に原発反対を示す内容のものを展示場側が強引に撤去を命じた事例。憲法21条に反することをメディアを通じて訴えたら撤回したらしいが、表現を圧殺しようとした履歴は消せない。しかも行政側の独断行為でこれが行われている。
・・・
・・・
・・・
どうしたんだ!ニッポン!
いいのかこれで。それでもあなたは与党に投票するつもりか?
★
貼りました。みつけてみてくださいね。
表現の不自由展① 平和の少女像
일본우익 협박 속 '평화의 소녀상' 7년 만에 도쿄에서 선보여 日本右翼脅迫の中で「平和の少女像」7年ぶりに東京で披露)Yonhapnews







(=^・^=)
貼りました。みつけてみてくださいね。
大島渚賞 絞死刑
三回目となる大島渚賞のトークイベントに参加することができた。会場は東京駅前、丸ビルホール。この建物に入ったのは初めてだと思う。
ところで、この記事も長いので読まないほうがいい。しょうもない記事だ。

エスカレーターで7階まで上ると目的のホールがある。

今年で3回めとなるこの賞は、ぴあの企画だそうだ。生前の大島渚監督のメッセージが流される。「言論から情報への変化」いつ頃の映像かわからないが大島渚はぴあに寄せてこのようなことを述べていた。大島渚が生きた時代は”言論”の時代だったのだ。今年の受賞作『海辺の彼女たち』の上映があって、その後黒沢清監督と大島新監督を交えて三人のトークショーがあったが、劇場を包む加齢の空気を見て、大島渚の言う言論、情報ときてネット社会の老人たちは何を思うのか、ぜひ聞いてみたいものだ。受賞作の監督藤元明緒氏はまだ32歳。彼が映画に大島渚作品に接したのは、学校の授業で見た『戦場のメリークリスマス』だったそうだ。そして彼らの世代は映画を見ないのだそうだ。テレビでたまたま見た映画、というきっかけが彼の映画への入口だったらしい。そう聞いてまた劇場を見渡す。となると、もはや映画は年寄りのささやかな娯楽ということか。確かにそうかもしれない。

大島渚作品を劇場でデジタル上映するのは難しいらしい。デジタル化された作品がそれほど多くない、という意味だ。数少ないデジタル化作品の中で、今年は『絞死刑』が上映された。奇想天外なドラマ。冒頭の死刑廃止に賛成か反対かの文字に続き、小菅にある死刑執行が行われる建物を空撮するシーンへ。そして死刑を執り行う建物をそのまま再現した部屋で大島渚自身がナレーションを行い、まさに死刑執行を行うまでのディテールを細かく解説してゆく。
1958年に起きた小松川事件を再現し、在日朝鮮人のRという未成年を絞首刑にするまでのシーンは息を呑む。まるで見る側がこの青年を殺そうとするかのような語り口に体が固まる。ラストでも大島渚は「あなたも」というナレーションで、この映画の本当の結論を見る側に委ねて終わる。
基本的にこれはドタバタコメディだ。死刑執行したら死ななかった、ということから混乱してゆうドラマ。密室劇。
しかし見る側は、この映画が露骨な日本の侵略、特に朝鮮人に対する愚かな行為について、殺人を犯したRを本当に死刑にしていいのか疑問を抱くように作られている。なぜならR以外の人物はこの映画で狂っているからだ。まともな人はだれも出てこない。このコミカルで愚かしい人物たちを日本人と位置づけ、死刑執行を待つRと対比させている。
ここまで見て、前日に鑑賞した「表現の不自由展」が重なってくる。日本人が朝鮮人に対してしてきた行為。それを置き去りにして、何事もなかったように自国の名誉を守るために慰安婦を連想させる作品などを強行に排除しようとする人たち。憲法9条をかたどるだけで、表現が封じ込められる。憲法21条の問題にすり替わる。
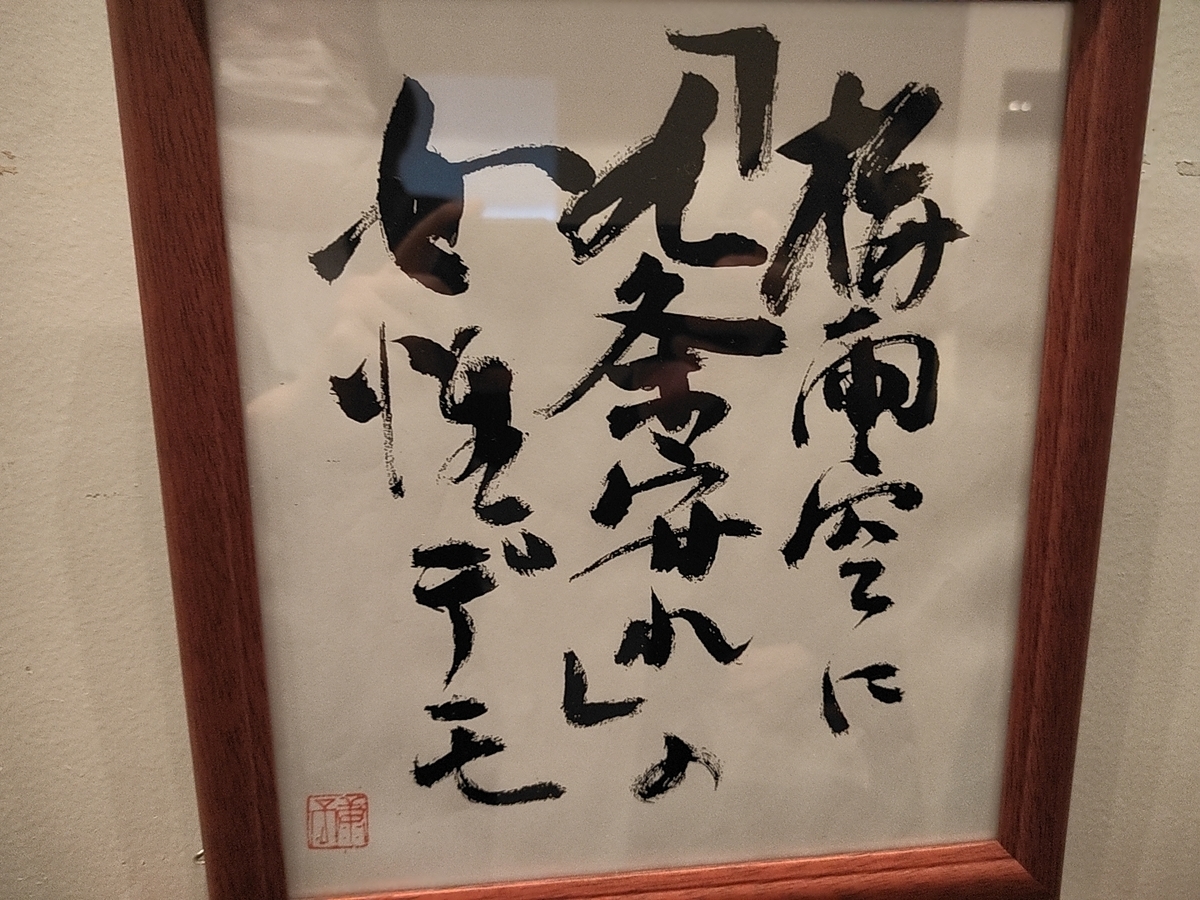
大島渚はこの『絞死刑』のみならず、大胆に時代を忖度なしに表現する。『愛のコリーダ』も然り。『愛のコリーダ』で描かれたのは単なるエロシチズムではない。本当に描こうとしたのは戦争だ。そしてこの『絞死刑』もまた戦争を物語るシーンがある。死刑執行する側の戦争体験が語られる。人を殺める、という行為が当たり前となる恐怖。そして意識を失っていたRが意識を取り戻したとき、自分の罪を認めつつ、その自分を死刑にしようとする人たちも同罪だと言い出す。死刑を執行する行為も殺人だ。死刑執行する人を殺人と位置づければ、日本人は全員人殺しになるという。

先人が犯した行為とはいえ、いまだに死刑が執行される日本に住む日本人は、よくこのことを考えたほうがいい。少なくともこの100年の間に、同じ血の流れる日本人は戦争をしかけて、多くの人種を殺してきた。そして自らの国民も殺してきた。この”殺す”という行為が我々の体に流れていることを忘れてはならない。この映画の主人公である在日朝鮮人は、日本人を”人殺し”と位置づけて問う。問われた側は茶番を繰り返し結論を出せない。

日の丸を身にまとって告白する在日朝鮮人のR。これはもしかすると傷痍軍人を重ねているのか。日本人として戦った傷痍軍人は、戦後行き場を失って路上で頭を下げる。『忘れられた皇軍』でも描かれたこの問題を、日本はまだ終わらせていない。昨今に至っては、時間がこの問題を解決するものとでも言うように、先送りを決め込んでいる。原一男監督の『水俣曼荼羅』でもそうした日本人らしさが描かれていた。

つくづく我々日本人はこれほど愚かなのかと思う。
★
貼りました。みつけてみてくださいね。