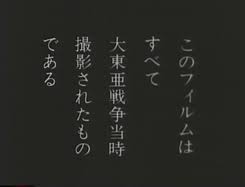いくつか驚くことがあるが、最も驚いたのは会場の熱気である。大勢のお客さんがぎっしり。

この大勢のお客さんがこのドキュメンタリー映像を真剣に見ている空気に圧倒される。この映画(ここではこれを敢えて映画と称する)は、当時のニュース映像をそのままつないでいるだけで、これらの映像に何もコメントしない。作り手の意見や、この映画が作られた時代(1968年)からは何も語らないという作りになっている。
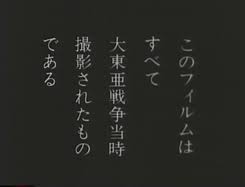

そしてこの語り口に惹き寄せられてゆくうちに、
軍国主義の日本人そのものになってゆく自分に気づいてドキッとする。”
君が代”や”
海行かば”が流れてくると涙がこぼれ、当時の人々と同じ感覚になってゆく。特攻隊として見送る立場であったり、少年少女の行進などをまるで自分のことのように思えてくるのである。
映像を見せて、見る側にシンクロさせてゆくという手法は大島渚の特徴とも言える。例えば『新宿泥棒日記』や『夏の妹』などがそれだ。主人公の少女をレイプしたいという気持ちを誘引するような展開にどぎまぎする。これは後の『愛のコリーダ』や『愛の亡霊』、その果てに遺作となる『御法度』までつながるものではないだろうか。大島は常に禁断のテーマを突きつけて見る側を脅迫するようだ。
www.youtube.com
大島渚研究の大作を作られた
樋口尚文氏の言葉にもある通り、
大島渚作品はひとつとして同じものがない。これだという作家性をほとんど無視して、変化し続けることを生涯のテーマとしていたようだ。それは奇しくも『
戦場のメリークリスマス』の
デヴィッド・ボウイと同じだ。

そしてこのドキュメンタリー映像は、日本が
大東亜共栄圏を死守して滅びてゆく過程を、ドラマ性を拒絶するように描かれている。戦後、戦争を語るのは容易いことかもしれないが、戦時中の日本人になってこの映画を見ると、愚かな行為も受け入れるようになってしまう。
プロパガンダの恐ろしさを見事に語り尽くす。さかんにナレーションされる「
大本営」という言葉は現実となる。

さらに忘れてはならないのは、この映画がいま我々の現実までも写しているということだ。我々はコロナのことをほとんど知らされていない。オリンピックのこともワクチンのこともまるで知らされていない。こうした報道についてメディアは政治とべったりくっついて受け手の立場を見ていない。そんなことを気づかせてくれる映画でもある。あらためて
大島渚の先見性を感じる。21世紀の日本は、
大東亜戦争時と同じメディアに騙されていて、それを誰も知らないという悲しい現実に浸っているのだ。
(=^・^=)
★

にほんブログ村

にほんブログ村

★